こんなお悩みありませんか?
心療内科・精神科へ初めて通う方の中には、うまく症状が説明できない方も多くいます。説明できないけどなんだかうまくいかない、いつもの調子がでない、というのは名前のない症状の表れです。
まずは心の声に向き合って、専門医にそれを話してみませんか?検査やカウンセリングを経てきちんとした症名が付くことで、あなたに合わせた治療法を一緒に探ってまいります。

症状について
About Symptoms
気分が落ち込む

普段は楽しめていた活動や趣味に対しても気分が上がらず、憂鬱な状態が長期間続く症状がみられ、日常生活や人間関係に支障をきたしている場合は、うつ病やその他精神的な疾患の可能性があります。医療専門家や精神保健専門家へ相談し、適切な治療を受ける事が大切です。
可能性のある病名
不安になる、緊張する

持続的な不安や緊張などが主な症状として現れる場合、パニック障害、強迫性障害などが考えられます。その他にもうつ病や発達障害の二次障害としての不安症状かもしれません。
可能性のある病名
やる気が出ない

自分から何かしたいという意欲や動機が低下し、あらゆる活動に対しての興味を感じられない状態は、抑うつ状態かもしれません。原因としてはストレスによるモチベーションの欠如の他、うつ病などの病気が考えられます。特に、原因なく長期間続く意欲の低下は、専門医療機関やカウンセラーに相談しましょう。
可能性のある病名
イライラする・怒りっぽい
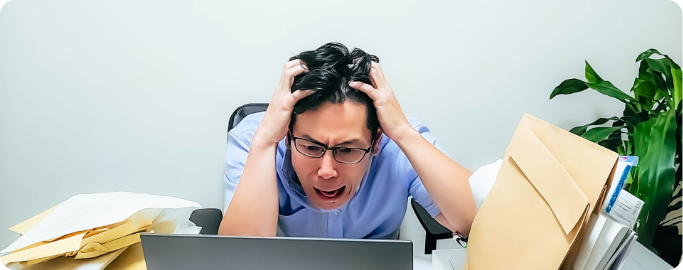
怒りやイライラした状態は様々な要因により引き起こされるものですが、長時間続く場合や日常生活・人間関係に支障をきたす場合は、ストレス・感情コントロールの困難、心の健康の問題、身体的不快感などの影響が考えられます。
可能性のある病名
集中力がない・ミスが多い

日常の活動において集中力が極端に続かない・維持が難しい、注意力が落ちて誤りやミスが頻発するなどの症状の原因として、ストレス、疲労・睡眠不足、またはうつ病や、発達障害に伴う実行機能障害が考えられます。集中して今までできていた読書やテレビ鑑賞などが困難になった場合には、専門家の助言や支援を受けることをお勧めします。
可能性のある病名
夜眠れない・日中の眠気

睡眠障害、特に不眠症状や日中の過度な眠気は誰にでも起こりうる症状ですが、持続的に症状が見られる場合は注意が必要です。例えば日中起きていられない・遅刻や寝坊が増えるなど、日常生活に支障をきたす場合は、うつ病、発達障害、睡眠障害などの病的なものが原因と考えられるため、専門医療機関や睡眠の専門家への相談が必要です。
可能性のある病名
病名について
About disease names
気分障害
(うつ病、躁うつ病)

うつ病とは、気分障害という病気の一つで、気分が落ち込んだり、何事にも興味が持てなくなったりする精神症状と、眠れない、食欲がないなどの身体症状が現れる病気です。脳内の神経伝達物質のバランスの乱れなどが関係し、日常生活に大きな支障をきたすため、専門家による早期の診断と治療が必要となります。
また、うつ病には2つに分類されており、うつ状態だけが続くものを「単極性うつ病」、うつ状態と躁状態(気分が高揚する状態)を繰り返すものを「躁うつ病」といいます。
不安障害

社会生活や人付き合いに強い不安を抱き、日常生活に支障を来す程度になると不安障害と診断されます。人前での立ち振る舞いにおいて恥をかくのではないか、拒絶されるのではないかといった恐れを常々抱いているのが社交不安障害で、汚いものに恐怖を感じたり、何度も確認行為をしてしまうのが強迫性障害です。他にも不安障害に分類されるものとしては全般性不安障害、パニック障害などがあります。
心的外傷後ストレス障害(PTSD)

心的外傷後ストレス障害は、生死に関わるような強い恐怖体験をした後に、その体験が忘れられず、フラッシュバックや悪夢、強い不安や緊張、現実感の喪失などの症状が現れる精神疾患のことです。幼少期に受けた虐待経験、または生死にかかわる事故や災害、戦争、犯罪などが原因で引き起こされます。 体験後、数週間から数か月経ってから現れることもありますので、同様の症状を認めた場合は専門医療機関に受診してください。
統合失調症

統合失調症は、思考、感情、行動などがまとまりを欠き、社会生活に支障をきたす精神疾患です。幻覚や妄想などの「陽性症状」、意欲の低下や感情表現の減少などの「陰性症状」、また注意力・集中力の低下や記憶力の低下、実行機能の低下など「認知機能障害」が現れることがあります。10代後半から30代に発症することが多く、早期の診断と治療が重要です。
適応障害

適応障害とは、ストレスが原因で、気分や行動面に症状が現れ、社会生活に支障をきたす状態のことです。具体的には、新しい環境への順応の困難さや、大きな変化に対するストレスが原因で、抑うつ気分、不安、不眠、食欲不振、無断欠勤、対人トラブルなどが生じることがあります。適応障害は「甘え」ではなく、「病気」にあたるので、専門の医療機関に受診をしてください。
依存症
(アルコール、ニコチン等)

依存症とは、特定の物質や行為に対して、やめたくてもやめられない状態になる病気のことです。アルコール、薬物、ギャンブルなど、様々な依存対象があります。依存症は、脳の機能に変化が生じることで、自分の意思だけではコントロールすることが難しくなります。依存症は、誰でもなりうる病気であり、意志の弱さや性格の問題ではありません。また、患者の家族も巻き込まれることにより疲弊してしまうこともあります。お困りのことがあれば専門家による治療やサポートを受けることが重要です。
発達障害

発達障害とは、生まれつき脳の機能の発達に偏りがあり、そのために行動や思考、感情などに特徴が見られる状態のことです。自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などが含まれます。これらの特性は、日常生活や社会生活に困難をもたらすこともありますが、適切な理解と支援があれば、個性として輝くことも可能です。
睡眠障害

睡眠障害は、睡眠の質や量が低下し、日中の活動に支障をきたす状態を指します。寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、熟睡できない等の「不眠」、日中に強い眠気を感じたり居眠りをしてしまう「過眠」、また睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群などの「睡眠妨害」、悪夢やレム睡眠行動異常、昼夜の逆転・不規則な睡眠時間による睡眠・覚醒リズムの障害など、様々な疾患があります。

